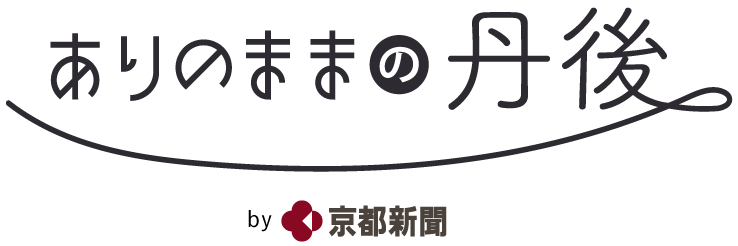2025.03.18|まち
春は祭り囃子に乗って
子どもの成長促す民俗芸能
知恵を集めて後世へ

春の祭礼で芸屋台とともに囃子を披露する高校生ら(2024年4月28日、与謝野町加悦)

屋台の上で歌舞伎を演じる小学生ら(2024年4月、与謝野町後野)
丹後の春は祭り囃子(ばやし)とともにやってくる。4、5月の祭礼を前に各地で囃子の練習が続く。軽やかに、時にゆっくり堂々と。繰り返す音色は三寒四温の歩調に重なる。
囃子に心揺さぶられる方もいるだろう。民俗学では、神霊を揺り動かす力を秘めるとし、地蔵や大木が動き出す狂言などもある。生命が目覚める今の時節は、特に心地よい。
京都府内の94の祭り・行事を調査した報告書を府教育委員会がまとめた。丹後では囃子に加えて、屋台を芸能の舞台として扱うと。そこで歌舞伎や手踊り、太鼓を演じるのは小学生だ。囃子方の中高校生と一緒に主役を務める。
祭りは子ども自身の成長にもつながる。技芸の習得を通じ、培われてきた知識や知恵を先輩から教わる。礼儀や作法、秩序に応じた行動を体得する―と報告書は記す。地域の支え合いを知る場なのだ。
思えば、東日本大震災の被災地では、民俗芸能がまちの再生に力を与えた。人々のつながりを結び直し、震災前の日常を思い出すよすがであり、離散しても故郷に戻るきっかけになる。
「変わらない伝統はない」。東北の民俗文化に詳しい高倉浩樹さんはみる。災害やコロナ禍、若者流出…。逆風の中、後世に残すために何を変えるか。囃子の音に心躍らせた、新たな担い手が現れることを願って。
Copyright ©京都新聞

丹後地域の祭り・行事を調査し、子どもが参加する意義を話す府丹後郷土資料館の学芸員(京丹後市大宮町)
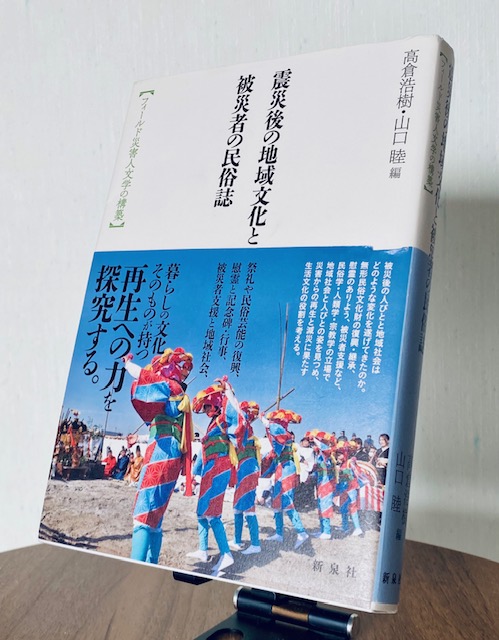
東日本大震災後の民俗芸能について記した高倉浩樹さん編集の研究書