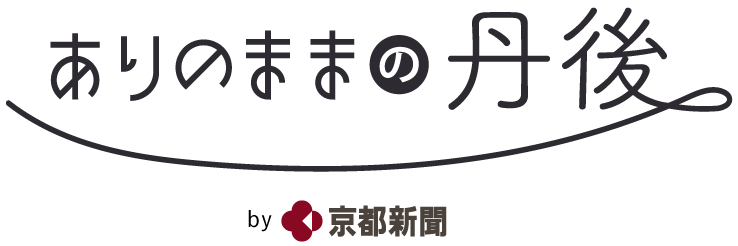丹後とり貝
今季の出荷断念
貝毒検出の舞鶴・宮津湾産
京都府漁業協同組合は、下痢性貝毒の検出で出荷延期が続いていた舞鶴湾産と宮津湾産の「丹後とり貝」について、今季の出荷を断念した。全体の約3分の2を生産する舞鶴湾産が出荷できず、5月から流通する久美浜湾(京丹後市)産に頼り、出荷量は前年比で8割以上減った。関係者からは落胆の声が上がり、有効な対策も無い中で来年に向けて準備を始める生産者には不安が広がる。

丹後とり貝は、京都府海洋センター(宮津市)が生産した稚貝を漁業者が1年弱ほど養殖し、5~6月ごろ出荷。高級食材として、首都圏でも消費される。久美浜湾産の出荷は6月中旬に終わり、今シーズンの出荷量は前年比約25万個減の5万個にとどまった。例年の出荷量は20万個程度という。
府漁協によると、舞鶴湾産について、初出荷前の5月7日の検体で基準値を超える貝毒を検出した。6月に入り下回ったが、16日の検体が再び基準値超となった。
各産地からの出荷には、1週間ごとの検査で3回連続、基準値を下回る必要がある。7月には海水温の上昇で貝が死ぬリスクが高まり、翌年の出荷分の準備を始める時期にもなるため、府漁協は出荷を断念した。千賀隼人組織部長は「6月下旬には出荷できると見込んでいたので、非常に残念で心苦しい判断」と話す。

府沿岸での下痢性貝毒の発生は2023年以来2回目だが、西日本の日本海側ではまれとされる。府海洋センターの谷本尚史主任研究員によると、特定の植物プランクトンが蓄積して毒化したことが原因だが、「プランクトンの発生や毒化のメカニズムがよく分かっておらず、有効な対策は無い」という。
生産した貝は焼却処分される。府漁協によると、保険が適用されるが漁業者の経営や心理への影響は大きく、「不安が広がり、生産意欲は落ち込んでいる」という。漁業者でつくる舞鶴とり貝組合の川﨑芳彦代表(71)も「仕方ないので(今季については)考えない。来年に向けて頑張るしかない」と話す。
道の駅「舞鶴港とれとれセンター」(舞鶴市下福井)の鮮魚店「魚たつ」の藤元達雄会長(77)は、「今年は出回る量が極端に少なく、とり貝を楽しみに来てくれる人にも提供できなかった」と振り返る。客には来年も来てほしいと伝えたというが、「来年も同じようなことになるとお客さんが離れてしまうのでは」と懸念を口にした。
Copyright ©京都新聞