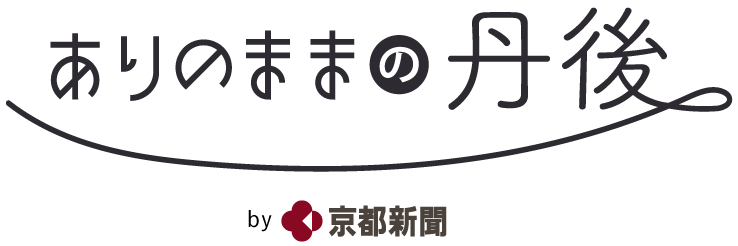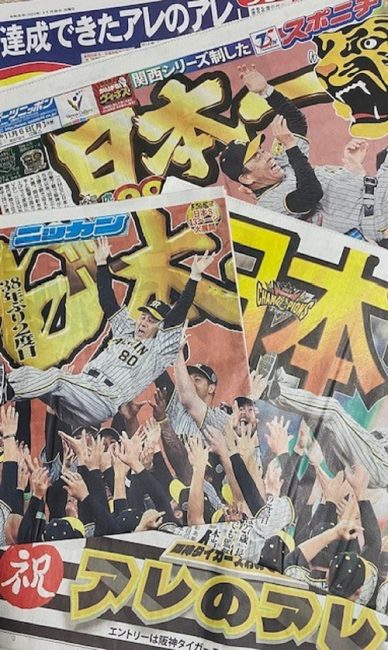広がれ、ユニバーサルサップ
京丹後の海で体験
高齢者、障害者も容易に
ボードの上に立って水面を進む「スタンドアップパドルボード(SUP=サップ)」。マリンスポーツとして全国に広がり、京都府北部でも体験できる。高齢者や障害者も一緒に海を楽しめる「ユニバーサルサップ体験」があると聞き、京丹後市で記者が体験した。(高桑啓樹)

透き通るようなエメラルドグリーンの海が広がる同市網野町浜詰の夕日ケ浦海岸。子どもの頃から泳ぐことは苦手だが、一般のサップに挑んだ。
マリンスポーツ体験を個人事業で展開する「京丹後135。EAST」の石川龍也代表(61)から手渡されたライフジャケットを身につけ、海沿いに並べられたボードを波打ち際まで引っ張って入水する。腰ほどの水深の場所で浮いたボードの上に慎重に乗った。
次は、安定感のある正座の姿勢になり、パドルを使ってこぐ。勢いがついてきたら膝立ちになり、最後に立ち上がる。スピードがつくと安定するが、油断して何度か転覆した。ボード上でバランスを取りながらこぐことは、高齢者や障害のある人にとって容易ではないことが身をもって分かる。
石川さんは昨年、障害の有無や年齢にかかわらず、「家族みんなで海を楽しんでほしい」という思いから、「ユニバーサルサップ体験」を新たに始めた。
用意されたのは、座いすが取り付けられたボードだった。通常のサップ同様、海面に浮いたボードに乗る。背もたれ付きの座いすに腰かけ、足を伸ばして座る。通常のサップよりも安定しており、安心して快走できる。

座いす付きのボードに乗ることが困難な人向けの「水に浮く車いす」もあった。ビーチチェアのような見た目のいすに、黄色いタイヤが三個付いている。水陸両用で、約20センチ幅の太いタイヤのため、普通の車いすのように砂浜に車輪がのめり込む心配もない。
インストラクターに押してもらい、車いすに乗ったまま砂浜から水へ。水深が深くなり、タイヤが底から離れると水上に浮かぶような感覚を味わえる。車いすには肘から手までをゆったりかけられる大きさのフロート(浮具)が両脇についているため、転覆する怖さもなかった。

水に浮く車いすを利用した人の評判もいい。3年前に脳出血で左半身が不自由な酒井博道さん(75)=同市網野町=は、今夏に水に浮く車いすを使い、小学生の孫2人と海水浴を楽しんだ。「海に入りたいという思いはあったが不安だった。孫と同じ目線で海に入れたことが何よりよかった」と笑顔を見せた。
ユニバーサルサップ体験の内容は、参加者個々に合わせて決めているといい、石川さんは「みんなで一緒に参加して楽しんでもらえればうれしい」と願う。
体験は9月末まで。
支援の取り組み 全国でも
ユニバーサルサップのような誰もがアウトドアを楽しむための取り組みは全国で広がっている。
神戸市を中心に活動するNPO法人・須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、車いす利用者の海水浴をサポートする。
車いすでも波打ち際まで移動できるように幅1・5メートル、長さ10メートルのビーチマットを敷いたり、水陸両用のビーチチェアを導入したりすることで、車いすの利用者が安心してビーチを使えるように工夫する。
障害のある人が楽しめるビーチの数は、全国的に増加している。「身体障害者向けのアクセスと設備」など33の基準を達成したビーチに与えられる「ブルーフラッグ認証」の数は、2016年は全国で2カ所だけだったが、現在は12カ所まで増えた。
車いす利用者によるアウトドア活動を支援する取り組みは海に限らない。
株式会社オートテクニックジャパン(栃木県)は、長野県の観光事業者らと協力し、アウトドア対応型の電動車いすを開発中だ。
車いすで生活している人たちに、林や沼地のような悪路も走行できる新機種を操ってもらい、「家族と一緒に自然体験を楽しむことができる社会を目指す」という。
Copyright ©京都新聞