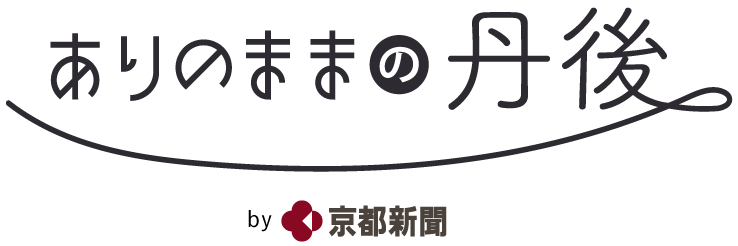シリーズ「発酵風土」㊦
酢の熟成 美食のまちへ
宮津・飯尾醸造

高い天井から、柔らかな明かりが注ぐ。
店内はカウンターの6席のみ。3年前、宮津市新浜にオープンした寿司割烹「西入る」で、ポルトガル出身の料理人、リカルド・コモリさん(44)が黙々とネタを握る。
独自にブレンドした酢の香りと、魚のうまみや甘み。それらが口内に広がる一品は、食通をうならせる。店は世界的なレストランガイドで紹介され、評価も高まっている。
リカルドさんの腕を支えるのは、地元に揚がる魚介類。日々、早朝から栗田漁港に足を運び、目利きする。「ブランド品でなくても、素晴らしい」。アジやイカを新鮮なまま締めて持ち帰る。

「このまちを変えるきっかけになる、料理人を求めている」
東京や京都の店で修業したリカルドさんを口説いたのは、飯尾彰浩さん(49)だった。
飯尾さんは明治の創業以来、130年にわたって酢を製造する飯尾醸造(宮津市小田宿野)の五代目。当主の熱心な依頼に、リカルドさんも「ここでは食材や調味料、酒、全てが高いレベルで手に入る」とほれ込み、一料理人として応じた。
店がある新浜地区は、かつて花街として栄え、昭和初期にはお茶屋などが60軒以上並んだ。戦後は飲食店街になったが、にぎわいは下火に。空き家は取り壊され、駐車場にもなる。そんな宮津の姿に飯尾さんは強い危機感を抱く。2016年、踊りの稽古にも使われていた築120年の町家と蔵を自社で買い取った。
この2棟で、夕食限定の飲食店を仕掛ける。名勝・天橋立を見て日帰りするのではなく、「旅の目的になる飲食店が必要」。東京からシェフを招いて母屋でイタリア料理店を、蔵では「西入る」を開いた。
飯尾醸造も、丹後の風土や環境とともに歴史を刻んできた。
看板商品の「富士酢」は、契約農家が手がける無農薬の米と、宮津、舞鶴両市の境にある由良ケ岳の伏流水が欠かせない。「酢づくりは地元の農業とともにある文化」と飯尾さんは今も思う。
舞鶴に接する由良地区の酒蔵では今の時季、1月から4月まで杜氏が清酒を仕込む。隣の栗田地区にある酢蔵で、タンクにこの清酒と水、種酢を加える。そこに酢酸菌膜を浮かべ、4カ月かけて発酵を促す。昔ながらの「静置発酵」だ。
「発酵は原料の可能性を引き出す。五感を使い、酢をつくる菌が一番心地よい状態を整えるのが大切」
さらに、熟成蔵で約8カ月。飯尾さんも適宜、蔵人と試飲して品質を確かめ、まろやかな風味に仕上げる。
質の高い食材、調味料を料理人が操り、味わい深い逸品を創り上げる。「『料理人を満足させる魚や野菜を用意したい』と触発されると、漁業や農業も底上げされる」。
刺激と熟成。それぞれ一流の、職の結晶を丹後で。美食のまちづくりに力を注ぐ。
Copyright ©京都新聞