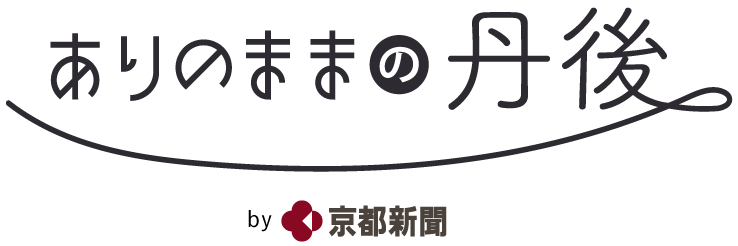どうして網野を選んだの?京丹後で人気の移住地、ワケを探った
2022年度、京丹後市への移住者が過去最多の52世帯88人となった。新型コロナウイルス禍で生活や働き方を見つめ直し、豊かな自然を求める人が多いという。中でも、網野町は15世帯29人と合併前の旧6町の中で最も多い。きれいな海にコンパクトにまとまった街並みが人気のようだ。実際の生活はどうだろう。移住者に魅力を聞いた。
タカとともに豊かな自然を求めて 新天地で「鷹カフェ」開業
好天に恵まれた5月下旬、京丹後市網野町浅茂川の八丁浜海水浴場で多くの親子連れが砂浜のごみ拾いに汗を流していた。そんな中、タカを腕に携えた男性が颯爽(さっそう)と現れた。参加者は「鷹匠だ」と目を奪われた。
その正体は村上健介さん(43)。3月末に家族で移住し、妻の聖子さん(40)が7月中旬にタカやフクロウといった猛禽類と触れ合える「鷹カフェ」をオープンした。1000円で「ミニ鷹匠体験」もできる。
移住のきっかけは長女の心夏さん(13)とタカの「ルカ」(2歳・雌)。心夏さんは鷹狩りの動画を見て関心を抱き、20年11月から京都府福知山市夜久野町の鷹匠に弟子入りした。タカを腕に乗せたり放って戻したりする技を練習している。
21年9月にはルカを京都市内で飼い始めた。だが、心夏さんは「もっと自然の中で育てたい」と健介さんに直談判した。
家族にとって、縁のない土地への移住は大きな決断だった。ただ、月4回キャンプに出かけるほどの自然好きで、京丹後市網野町の琴引浜や久美浜町の兜山でテントを張った経験もあった。ちょうど、小学生の長男と次男も昆虫探しにのめり込んでいて賛成だった。
移住する上で外せない条件は三つ。「京都府内で日本海側」「食事がおいしい」「子どもたちの学校が徒歩圏内」。この条件で、京丹後市と宮津市を中心に新居を探した。そして、網野町が当てはまった。
健介さんは当初、地元住民にタカを飼うことへの理解を得られるか不安だった。ところが、近所の人は「田んぼで飛ばしてくれてええで」と応じてくれた。移住前の昨年10月には町内会長の誘いで地域の祭りにルカとともに参加。「既に住んでいる感じでした」と、距離の近さをありがたがった。
「網野には海水浴やカニと、十分な観光資源がある。そこに、ちょっと違った体験を提供できたら」と健介さんは来店を心待ちにする。


海沿いが人気+コンパクトな街 地元不動産、空家バンク登録に力
移住施策を担当している京丹後市政策企画課に聞くと、移住希望者の多くは海を求めてくるという。自然やマリンスポーツ、海産物といった「ならでは」が引きつけている。
実際、22年度の移住者は、日本海に面した網野町、久美浜町、丹後町を合わせて53人と全体の6割を占めた。
「移住の相談件数は網野と久美浜が同じくらいです」。峰山町にある市移住支援センター「丹後暮らし探求舎」で移住相談員を務める小林朝子さん(40)が教えてくれた。「ただ、いざ物件を探してみると、網野町の方が多く、それが移住者の多さにつながっているのかもしれません」。
市の空き家情報バンクを調べてみると、全物件92件(7月19日現在)の中で網野町が最も多く27件。次いで丹後町20件、久美浜町17件と続く。
網野町はかつて網野、浅茂川両地区を中心に地場産業の「丹後ちりめん」の製造が盛んだった。多くの職人が家を構え、一帯は今も民家が密集している。現に、15年までは市内唯一、面積に対する人口の多さを示す「人口集中地区」だった。
少子高齢化や転出により空き家が増え始める中、バンクと提携している地元の不動産会社2社が奮起していると小林さんは指摘する。所有者と積極的に交渉し、登録数の増加に寄与している。
最近では芸術家からも注目を集める。機織り工房を併設した民家が点在し、その工房をアトリエにしたいと相談する人が増えているというのだ。
何を隠そう、小林さんも15年に網野へ転居した移住者だ。「きれいな海辺に溶け込んだ昔ながらの街並みがお気に入りです」。

子どもに、未来に残したい海 環境に目覚めた地域起こし協力隊
19年11月に地域おこし協力隊として移住した八隅孝治さん(37)は、どっぷりと海に心を奪われた。
移住前までは京都市消防局の救急救命士として活躍していた。10年前から妻の実家である久美浜町へ遊びに行くようになり、「将来はこの自然豊かな地で過ごしたい」との思いが芽生えた。
「引っ越した頃はカフェやゲストハウスを経営したいと思っていました」。そうぼんやりと思い描きつつ、子どもたちと海で遊ぶ日々を過ごした。
透き通った水面に、すいすいと泳ぐ魚の群れ、ほてった体を心地よく冷まし、子どもたちはいつまでも元気に遊ぶ。「これこそ、まさに幸せな時間でした」と八隅さん。
ふと砂浜に目をやると、プラスチックごみが落ちていた。生まれてこのかたボランティアすらしたことがなかったが「きれいなままの海を未来の子どもたちに残したい」との感情があふれた。
以来、八隅さんは海岸清掃やリサイクル、子ども向けの環境学習会にのめり込んでいった。住民団体「MOYAKO」を発足し、月1回、住民を集い海水浴場のごみ拾いを続けている。今では150人近い参加者が集う。さらに、年1回、車でのごみの搬送ができない「水晶浜」を「バケツリレー」で回収する取り組みにも力を入れる。
さらに、プラごみが最終処分場でたまり続けているという現状を知った八隅さんは「限りなくゼロの形にしなければ意味がない」と、今度はプラスチックを加工し、タイルやアクセサリーに再利用する「プレシャス・プラスチック」という事業に乗り出した。自宅横の元機織り工場を借り、機械を導入して製造している。
体験会も催しており、子どもから学生、社会人まで見学に訪れるという。八隅さんは「体験を通じて、環境美化に向けて自分にできることを考え、実行してもらえたら」と期待する。
昔は街の歩道に落ちたごみを気にも留めなかった。今では「ふるさと」の環境を誰よりも考える。「四季にも影響を受けました。冬、どんよりとして海も荒れまくる。だから、穏やかで透明な海を見たとき、いつも以上に感動する。きれいにしなきゃと思えます」
「一度きりの人生、自ら選択肢を選ぶ」がモットーの八隅さん。未来の子どものために、宝の海をみがき続ける。

ゆったり流れる時間、人情にほれる 京の提灯職人、新たな一歩
「町のゆっくりした感じというか、ふわ~っとした空気感が好きですね」。提灯職人の小嶋俊さん(38)が振り返った。黒を基調にした工房では、祭提灯の文字入れや、骨となる竹を糸でくくり付ける「いとつり」にいそしむ職人たちと小嶋さんの笑い声が響く。
小嶋さんは江戸後期に創業した京都提灯製造販売「小嶋商店」の10代目だ。京都市東山区の「南座」の正面玄関にある大提灯を手がけていることで知られる。
小嶋さんは、コロナをきっかけに21年に京都市内から移住し、同年10月に新たな工房「小嶋庵」をオープンした。元々、青く透き通った八丁浜の海が好きで「移住をするならここ」と決めていた。その浜辺から徒歩5分の場所にある、丹後ちりめんの機織り工場だった物件を購入。1階を工房に改修し、2階を居住スペースとした。
実際に住み始めて2年近く経過した。豪雪に荒れる日本海が来たかと思えば草木の香りが漂い始める春。夏の積乱雲と、くっきりと五感で感じる四季も気に入った。
何より、住民の人情にほれた。地域の祭や地蔵盆と、あまたある行事にもみんな全力だ。小嶋さんは今年、地域の催しをつかさどる「愛護会」の委員長に就任した。「みんな、いつでも相談に乗ってくれて協力的。昔ながらの日本のよい部分が残っている感じです」と顔をほころばせる。
のんびりと時間が過ぎ、子どもたちが外で遊ぶにも、海も公園も広々として自由にできる。京都での暮らしは時間に追われた。子どもたちと公園で遊ぶにも周囲に気遣い、少し窮屈な心地がした。今では子どもが友達を連れて工房で遊ぶ時もある。
現在、小嶋庵には5人の職人が研さんを積む。師弟関係やシフトといったものは存在しない。みな子育て世代の母親で、来られる時に仕事をしてもらっている。
提灯が完成するまでには約10工程ある。その中で得意な分野を見つけてもらい、技術を伸ばしていくスタイルをとっている。「お母さんは最強ですから、どんどん上達していって、今までにない提灯ができますよ」と小嶋さんは笑った。
京都にいた頃、小嶋さんはとがっていた。「提灯を見ただけで誰もが小嶋商店だと分かる、唯一無二の提灯を作ることばかりを考えてきました」。
このマインドは今も健在だ。ただ、すぐに溶け込んでくれる住民たちと、ゆっくりと流れる時間を過ごす中で考えは少し変わった。キャンプで使える防水タイプや、夜に授乳する時、赤ちゃんを起こさないよう優しく照らすものと、知人から「こんな提灯があったら」との意見を聞くようになった。そして「無二の提灯が一家に一つあってもいいじゃないか」と思うように。
将来的には、小嶋庵の職人たちと小嶋商店とが連携して、これまでにない提灯を作れたらと想像を膨らませる。小嶋さんはゆっくりと、新たな道を切り開いている。

「新しいもの好き」のDNA 移住者と住民の融合で活性化
移住相談員の小林さんは、網野町での生活を通じて、丹後人の気質を「古代、文化の玄関口だったため、新しいもの好きのDNAが宿っている」と考えるようになった。新しい事業や仕事に挑戦しようと移住した人を、地元住民は面白がり、仲間に加わろうとする。そんな気質があると分析する。自然と移住者を応援しているのだ。
この地には人生を変える住まいがあるようだ。
Copyright ©京都新聞