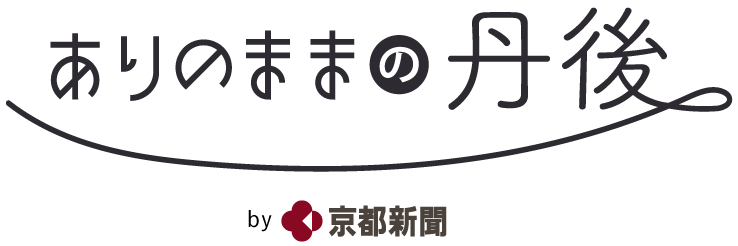シリーズ「発酵風土」㊤
浅漬けへしこ 風味一心
工房HISAMI

伝統の味は、各時代の嗜好(しこう)や調理法の変化にも応じながら受け継がれてきた。
丹後の郷土食の中で、わずか1年で別の料理かと思われるほど見た目や風味を変えた一品がある。京丹後市丹後町間人の「へしこ工房HISAMI」で、若き兄弟2人が開発した現代風の「旨米鯖(うまいさば)」だ。
誕生のきっかけは、新型コロナウイルス禍だった。
「これはちょっと、やばいかも…」。販売・企画担当の弟、今出健太さん(34)はつぶやいた。2020年春以降、都市部のデパートで催事はほぼなくなり、出店していた店舗兼工房の売り上げが激減していた。
催事で悔しい思いをしたこともあった。試食を勧めると「『へしこなんて』とドン引きされた」という。年上の世代の客にとって、舌がしびれるような塩辛い食べ物という印象しかなかったのだろう。
さらに、「若い世代にへしこ自体が知られていない」という危機感が兄弟の背中を押す。料理人で製造担当の兄、昌宏さん(37)は、コロナ禍を「へしこの印象や風味を変える良い機会」と捉え、二人で新商品の開発を始めた。
丹後のへしこは、塩漬けにしたサバをさらにぬか漬けにする。通常、ぬか床で半年から1年ほど発酵させるが、今出家に伝わるのは、熟成期間を約1カ月と大幅に短縮した「浅漬け」と呼ばれる調理法だ。
曽祖母の故ひさこさんが約70年前に作るようになり、近隣で振る舞った。父の龍(たつる)さん(64)が15年前に商品化した。子どもの頃から慣れ親しんだ「柔らかくクセのない逸品」に、兄弟は独自の工夫を加えていった。
「発酵食同士を組み合わせれば、相乗効果で新たな風味を生み出せる」。
都会で10年、和食とフランス料理の修業をした昌宏さんには確信があった。「もっと大胆に風味を変えてみては」と、洋菓子職人だった健太さんも提案。ぬか床に白ワインやヨーグルト、ナンプラーなどを組み合わせ、まろやかな風味に仕上げた。
試行錯誤の末、和食の枠を超えた「旨米鯖」が完成した。21年春に発売すると幅広い世代に支持され、京丹後市のふるさと納税の返礼品にもなっている。「バターと相性が良く、ムニエルやソテー、パスタなど洋風料理にも使える」と健太さんは話す。
「オイル漬け」「ピクルス」「リエット」といった派生商品も次々に生まれた。丹後のほかの地魚を食材にした商品開発も進んでいる。「へしこは素材のうまみに幅と奥行きをもたらす。可能性をもっと試したい」と昌宏さん。
曽祖母から受け継いだ技をさらに高める兄弟、その歩みは始まったばかりだ。
Copyright ©京都新聞