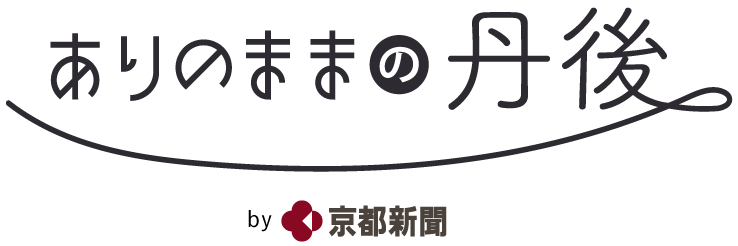不要な陶器に新たな価値を
芸術家らが再焼成
「サイネンショー」の現場に密着


不要になった陶器を穴窯で再焼成し、新たな価値を生むプロジェクトが京丹後市で10年以上続いている。陶芸家や美術作家らが取り組むプロジェクト名は「サイネンショー」。窯の中で陶器は名前のごとく炎であぶられて再燃焼し、薪の灰が降り注ぐ。美術作品のオブジェや一風変わった実用の器に変ぼうする現場に密着した。
5月上旬、京丹後市久美浜町にある山間の穴窯。主宰するのは、京都芸術大教授で、滋賀県立陶芸の森館長の松井利夫さん(69)で、京都府内の陶芸家やアートに関心を持つ人々が集まった。
窯の前には、家庭に眠っていたり、旅館で使われなくなったりして全国から寄せられた陶器がずらりと並ぶ。キャラクターがプリントされたコップや欧風の皿、見事な絵付けが施された大皿のほか、縄文土器のレプリカもある。
作業は古民家から出た廃材をチェーンソーで薪にすることから始まる。器にさまざまな釉薬をかけ、一部は絵付けもして窯に棚を組んで詰めていく。着火後はたき口から薪を入れる作業を繰り返す。
窯を管理する京丹後市久美浜町の陶芸家阪井義彦さん(62)らと一緒に私も薪をくべた。肌が焼けるほどの熱さの中、たき口から見える陶器は高温で白く発光しているかのよう。神秘的な炎の揺らめきに見とれてしまう。阪井さんは煙道の大きさを変えて窯の中の燃焼を調節する。焼成は40時間を超え、温度は1340度に達した。


溶け合い表情変える器
薪くべて非日常を体験


5月下旬の窯出しの日。松井さんは「よう溶けとる」と陶器の様子を見ながら、窯を開けていく。灰をかぶって薄緑の渋みが加わった茶わん、絵付けが色あせ、抽象画のようになった皿、くっついたコップ、ひしゃげた急須…。様変わりした逸品が次々と運び出されていく。
「きれいなゆがみや灰の掛かり具合がポイント。絵柄が流れる『泣き』の模様も特徴です」と語るのは、展示企画を担う美術家小山真有さん(40)。15回を重ねた今回の仕上がりを、松井さんは「上出来」と評価した。
始まりは2011年の東日本大震災だった。松井さんは復興支援で京都造形大(当時)の学生や陶芸家と被災地に器を送るプロジェクトに取り組んだ。活動資金を捻出するため、京都市内の百貨店で器の販売会を行うと、購入者から「いらなくなった器を引き取ってほしい」との要望があった。1996年に自身が制作に携わった久美浜町の窯で焼き直す試みを思いついた。
穴窯にこだわり
社会への問いも


陶芸で主流になった電気窯を避け、穴窯を選んだのは東京電力福島第1原発事故の影響だ。「復興支援なのに原発で発電した電気を使うのはあかん」と松井さん。2013年に初回の窯をたくと、作為的には「絶対に作れない器」が現れた。
窯をたくメンバーは陶芸未経験者も含み、入れ替わるのもプロジェクトの特徴だ。今回は府内のほか東京や秋田、鳥取、奈良から計14人が参加。鳥取県湯梨浜町のゲストハウス「たみ」を営む蛇谷りえさん(40)は「薪を割り、器に絵柄も施して楽しかった。人との出会いや、完成した器の語り部になれるのもいい」と語る。
松井さんは「窯をたくプロセスにも価値がある。固定化した日常の役割から離れ、自由になれる。窯の回りでいろんな『私』を体験できる」と言う。
作品は京都市や大阪市、東京都の現代美術やクラフトのギャラリーなどで展示され、都内の美術館のコレクションにも入った。曲がった一輪挿しを見て高値で買っていた器の提供者もいたという。
思想家・柳宗悦が唱えた「民藝運動」では、手仕事の生活道具に「用の美」を見いだした。松井さんはサイネンショーを「無用の美」と表現する。「世間では役に立つ、便利がもてはやされるが、役立たずのものにも美はある。捨てられるごみの中にも仏が入っている。求めて掘り起こさないと美は生まれない」と強調する。
サイネンショーは炎を扱う窯の魅力に人が集い、陶器の価値を反転させる。現代社会や美への問いかけもはらんでいる。
<メモ>
サイネンショーの器は6月下旬にオープンする秋田県五城目町の宿泊施設「市とコージ」で使用されるほか、10月に鳥取県のゲストハウス「たみ」で展示予定。2022年には10年間の活動記録をまとめた本「ザ・サイネンショー」(3520円、一般社団法人きりぶえ発行)が出版されている。哲学者の鷲田清一さんらが寄稿し、コミュニティデザイナーで関西学院大教授の山崎亮さんと松井さんとの対談も掲載している。
Copyright ©京都新聞